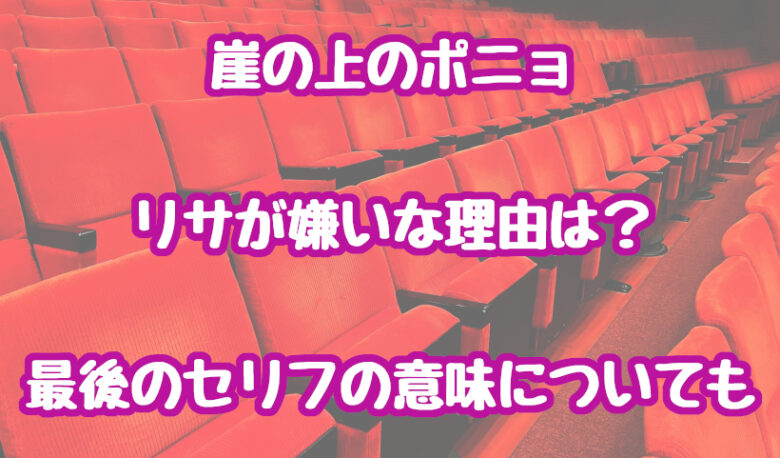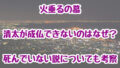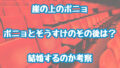スタジオジブリの名作であり、幅広い年代から人気を集めている「崖の上のポニョ」。
独特のファンタジーとユーモア、そして人間らしい感情が丁寧に描かれています。
物語は少年・宗介と不思議な魚の少女・ポニョの交流を軸に描かれますが、その中で宗介の母親・リサはたびたび話題に上ります。
リサの振る舞いや考え方は「嫌い」「共感できない」といった批判も根強く、その理由や背景、結末の象徴的なセリフに注目した人も多いことでしょう。
リサがなぜ嫌われるのか、考察します。
さらにリサの最後のセリフの意味について解説・考察します。
現代社会と映画の価値観の違いもふまえつつ、より深い作品理解のための手がかりになれば幸いです。
目次
崖の上のポニョ/リサがクズで嫌いと言われる理由
新作に備えて〜「崖の上のポニョ」編
ポニョと宗介にまっったく感情移入できなくなってて悲しくなりました。
逆にリサやフジモトの気持ちが分かってきてそれはそれでよかった。フジモトなんか悪役っぽいけど普通に良い人なんだね。
ただ、宮崎ジブリ作品の中で1番面白くないなって思うのはこれかも pic.twitter.com/D97BidXrsW— 涼風 (@Teto_0627) July 13, 2023
荒々しい車の運転が視聴者を不安にさせる
リサが批判される最大の理由のひとつが、作品序盤で見せる「無謀な運転」。
嵐のなか激しい雨が降る中で宗介を助手席に乗せ、帰宅を急ぐリサ。
しかし踏切や見通しの悪い山道を猛スピードで進み、波が押し寄せてくる危険な道を平然と進んでいきます。
この行動は特に子どもを持つ親世代から「現実離れしていて真似したくない」「危険すぎる」と受け止められがち。
加えて車中でリサが宗介を励ましたり状況を説明するリアルなやりとりも、逆に「楽観的すぎる」と取る層もいます。
作中の緊迫した嵐の表現と相まって、この運転シーンはリサへの疑念や不安感をより強く印象付けています。
小さな子どもを自宅に置いて出かけていく
もう一つ、リサに対する批判の大きなポイントは、嵐のなかで宗介を家に残し自ら老人ホームに向かうシーン。
- 5歳の宗介を一人で家に残すなんて信じられない
- あまりにも無責任
と、母親像に対する強い反発の声も少なくありません。
津波の脅威が迫る中、リサは介護士としてお年寄りを守る責任感を優先しますが、現代的な家庭観や感情から見れば、共感が得られにくい場面です。
一方でこの行動を「プロとしての責任感の強さ」「全体を守る母性」と評価する意見もあります。
作品が描こうとしたのは、単なる「優しい母親」ではなく、厳しい状況でも行動し決断する“生きる力”なのかもしれません。
正体不明の少女=ポニョを即座に家に迎え入れる
リサは、海から現れた見ず知らずのポニョをすぐに家に招き入れます。
これも現実社会とは大きく異なる価値観で、「子どもの安全を考えれば警戒心を持って当然」「よく考えずに行動しすぎ」と違和感を持つ人が多い点です。
現代的な危機管理の視点からすれば、無謀にも見えます。
しかし、困窮した人をすぐに受け入れるリサの人間的な温かさ・寛容さを評価する声もあります。
これは昭和的な日本の家族観や、宮崎駿監督が過去の作品でもしばしば描いてきた“共生”や“思いやり”を体現しています。
宗介が親を名前で呼び捨てで呼ぶ違和感
宗介が母・リサや父・耕一を名前で呼び捨てにしている点も、家庭文化によって大きく意見が分かれる部分です。
「一体どんな家庭教育なんだ」と驚きや戸惑いを覚えた人もいるでしょう。
ただ、これには宮崎駿監督ならではの意図があり、親子関係をより対等なものとして描きたいという演出意図が込められています。
結果として、家庭の距離感や親子の形が多様であることを考えさせてくれる場面でもあります。
「崖の上のポニョ」リサの人物像と背景をさらに深く読み解く
幼い頃よくポニョを見てたのだけどリサがソフトクリームを舐めとるシーンがとてもエッチだったから身体全体がゾゾゾゾってなってた(,,-_-,,) pic.twitter.com/MzFEgypSLk
— トロ (@ootoro1216) September 27, 2024
強さとやさしさを併せ持つ母親像
リサは作品内で「厳しい現実に立ち向かう強さ」と「他者への温かさや責任感」をあわせ持つ人物として描かれます。
嵐のなか、ためらわず行動する決断力。お年寄りや困った人を助けようとする優しさ。
現代のドラマやアニメではあまり見かけない、戦前・戦中の日本人女性に通じるような生命力と奉仕精神が特徴的です。
これは「お母さんは何があっても家族やコミュニティを守る存在」だった当時の理想的母親像にも通じる要素で、監督自身の体験や思い入れが垣間見られる部分です。
作品内の世界観が前提としている価値観
「崖の上のポニョ」は現実とファンタジーが混じる独特な世界。
物理法則や社会的な常識も、あくまで映画の“世界のルール”として限定的に表現されています。
だからこそ現実とのギャップでリサの行動に違和感を覚える人もいますが、監督は「社会の規範」よりも「人間の情熱」や「直感」を大切に描いていることが多いです。
現実社会の目線と物語の世界観の違いを認識することで、リサの違和感ある振る舞いも「この物語ならでは」と納得しやすくなるかもしれません。
家族や社会の中の役割を背負うリサ
リサの夫・耕一はたびたび家を空け、家庭内に不在感があります。
その中でリサは、母として、そして地域社会の一員として自ら行動します。
この「誰かがやらなければならない役割」を自然に担う姿こそが、リサらしさです。
子どもに対し過度に干渉せず「信じて見守る」姿勢や、周囲を励ます明るさも物語の強い印象を作っています。
つまりリサは「現代的な理想の母」とは違うかもしれませんが、非常時や困った時に人間として強く生き抜く姿を体現したキャラクターと言えるでしょう。
リサの「最後のセリフ」に込められた意味
【崖の上のポニョ リサ】 宗介さ、運命っていうのがあるんだよ。つらくても運命は変えられないんだよ pic.twitter.com/TsvIMvgJwx
— ジブリ名言bot (@sfdgfgfyhdasfga) August 17, 2019
最後の場面でリサがかける言葉「あなたも!グランマンマーレ!」
物語のクライマックス、ポニョの母である「グランマンマーレ」との対話の中で、リサが放つ「あなたも!グランマンマーレ!」(または「あなたもね!グランマンマーレ!」)という一言。
このやり取りはラストの印象的な場面のひとつで、母親同士の不思議な連帯感を感じさせます。
グランマンマーレから「リサ、ありがとう」と感謝の言葉を受け取るリサ。
それに呼応する形でリサは振り返りますが、決して下手に出るのではなく、対等にエールを送り返すその姿勢がとても印象的です。
母親同士の共感と連帯のメッセージ
このセリフには、母として子を見守り育む気持ち、そしてそれを遠くから共感し理解し合う「母親同士の連帯感」が込められています。
グランマンマーレもまた母として自らの子や全ての命を思いやる存在。
こうした母性の相互理解を通して、異質な存在同士が「共存」しうることを静かに示しているのかもしれません。
日本の文化においては親しい者同士を名前で呼び合うことで関係の深さを示す場面も多く、リサとグランマンマーレにも対等で親密な関係性が生まれていたことが暗示されています。
「崖の上のポニョ」ラストシーンから読み取れるメッセージ
久しぶりの友だちと連絡することが多くて、凄く嬉しい😽
会いたいとか、幸せだねぇ💞ポニョ見ててやっぱりリサ好き!ってなってた🫧
強くて優しくて可愛くて…
憧れる!
大波ザブン🌊のシーンで🚙爆走してるところ夫に「同じことしそうだよね」て言われた笑
私はそんなカッコよくないよ?😇 pic.twitter.com/Nna9mnnjZN— とも (@nagasawa63) June 21, 2025
「リサさん辛いでしょうね」に込められた複雑な感情
リサが老人ホームでお年寄りにかけられる「リサさん辛いでしょうね」というセリフ。
この一言は、単なる同情ではなく「母親として宗介に大きな試練を与えねばならない心の葛藤」や「運命に背中を押すしかない苦しさ」といった複雑な心情を代弁しています。
宗介がポニョの本当の姿を知れば、彼女は泡となってしまう危うい運命。
「宗介を信じるしかない」母としての心の強さと弱さを、映画の静かなシーンに重ねて描かれています。
親子の信頼や「子どもの自立を見守る」ことの難しさがこの台詞に凝縮されているのです。
宮崎駿監督が描くハッピーエンドの意味
「崖の上のポニョ」は「人魚姫」にインスパイアされた物語ですが、オリジナル版の悲劇的な結末には納得できなかったという宮崎駿監督。
だからこそ、最後は宗介とポニョが幸せに暮らすハッピーエンドに強くこだわりました。
この希望に満ちたエンディングには、“子どもたちの力で未来は変えられる”“大人たちはそれを信じて見守るべき”というメッセージが重なっています。
リサも「葛藤や不安を抱えながら、子どもと運命を共に歩む親」の象徴として、本作の核となる存在です。
まとめ
ラストシーン🎞で悩んでいた #宮崎監督🎬に #鈴木敏夫 プロデューサーが「普通、海からやってきたら海へ帰るんじゃないですか」と言ったところ監督🎬は「いや、帰らせない」と言いこのエンディングになったそうです🤗。→続く#金ロー#崖の上のポニョ#ポニョ#宗介 #リサ#宮崎駿#大橋のぞみ pic.twitter.com/WJpYAxIBi6
— アンク@金曜ロードショー公式 (@kinro_ntv) August 23, 2019
「崖の上のポニョ」に登場するリサは、非常時の大胆な行動や現代とは異なる母親像によって賛否が分かれます。
しかし、その背景には家族や社会への責任感、強さ、やさしさがしっかり描かれています。
ラストのセリフや行動には「母として子どもの成長を信じる気持ち」や「支え合いの大切さ」など、深いメッセージが込められています。
現実と物語の価値観の違いを踏まえて観ることで、リサの魅力や作品のテーマがより見えてくるでしょう。
最後までご覧いただきありがとうございました!