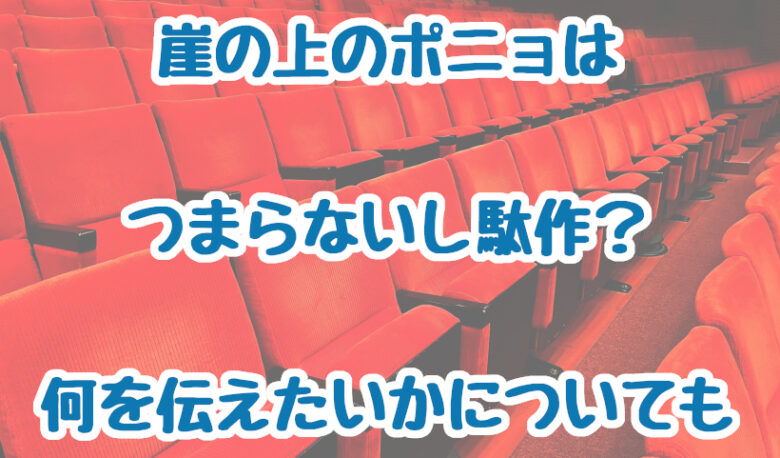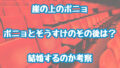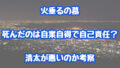映画「崖の上のポニョ」は、2008年に公開されたスタジオジブリの作品であり、宮崎駿監督が手がけた長編アニメーションです。
この作品は、独特な世界観やビジュアル、子どもらしい純粋なストーリー展開が評価される一方で、一部からは「つまらない」「駄作」といった否定的な声も上がっています。
なぜこのような二極化した評価が生まれるのでしょうか。
本記事では、「崖の上のポニョ」がなぜ「つまらない」「駄作」と言われてしまうのか、理由を考察します。
作品に込められた宮崎駿監督のメッセージについて詳しく考察します。
実体験や世間の評価も踏まえながら、改めてこの映画が伝えようとしたことを読み解いていきます。
目次
崖の上のポニョがつまらない・駄作と言われる理由を考察
ムム…これは坊ちゃんが絶対ハマるやつ🚢
8月22日金曜ロードショー「崖の上のポニョ」よる9時放送! https://t.co/VuvzFMRXGz #金曜ロードショー
— Momo96 (@momo96_fpnjn433) August 5, 2025
ストーリー展開のわかりにくさ
「崖の上のポニョ」に否定的な意見が多い理由の一つに、ストーリー自体の分かりにくさがあります。
ポニョという魚の子どもが人間の男の子である宗介と出会い、人間になりたいと願うファンタジックな物語ですが、従来のジブリ作品のような分かりやすい善悪や明確な目的意識が希薄です。
物語の構造が直線的ではなく、突如として場面が転換するなど、子ども向けとは思えない難解さを感じた視聴者も多いようです。
このため、「よく分からなかった」「何を描きたいのか分からない」という声が上がっています。
キャラクターへの共感のしにくさ
ポニョや宗介、リサ、フジモトなどの登場人物たちも、従来のジブリ作品に比べると感情移入しにくいという評価を受けることがあります。
宗介は純粋で健気な5歳児として描かれていますが、物語の中心でありながら感情的な浮き沈みが少なく、成長や葛藤の描写が薄いと感じられる場合があります。
また父親であるフジモトやグランマンマーレの存在も説明が不十分で、「なぜこうなったのか」という背景の説明不足を指摘されることも多いです。
大人目線で作品を見ることへの違和感
「崖の上のポニョ」は、そもそも大人よりも子どもたちに向けて作られているという点が大きな特徴です。
にもかかわらず、大人の視聴者が平均的な映画作品と同じように論理性や整合性、ストーリーの緻密さを求めると、どうしても物足りなさや違和感が残ります。
例えば、現実離れした状況に舞台が急転したり、物語途中で説明されないまま事態が解決していく場面などは、大人にとって腑に落ちない部分かもしれません。
こうした点が「つまらない」「駄作」と感じられる一因でしょう。
ジブリ過去作品との比較
◆『千と千尋の神隠し』が金曜ロードショーで放送!
日程:2024年1月5日(金)
時間:21:00~23:34(日テレ)https://t.co/hsmz86OaWY pic.twitter.com/szPMewUxZg— ジブリのせかい【非公式ファンサイト】 (@ghibli_world) December 8, 2023
どうしても他のジブリ作品、例えば「千と千尋の神隠し」「もののけ姫」「となりのトトロ」などと比べられることが多く、その結果として「ポニョ」はスケールが小さく見えてしまうという声もあります。
ストーリーやキャラクターの深み、社会的なテーマや問題提起の部分で地味に感じられてしまい、「物足りない」という評価が発生します。
アニメーション表現や音楽に関する賛否
「崖の上のポニョ」は全編手描きのアニメーションにこだわった作品で、デジタル技術に頼らない温かみのある映像が高く評価されています。
しかし、その一方でビビッドな色使いや大胆なデフォルメ、独特な作画タッチについて「子どもっぽすぎる」「荒い」という否定的な意見も見受けられます。
また主題歌「ポニョポニョ」で有名な明るくキャッチーな音楽も、雰囲気になじめないという意見が一部で挙がっています。
崖の上のポニョで宮崎駿監督は何を伝えたい?
映画鑑賞記録簿
No.831
【崖の上のポニョ】(2008)
宗介は、海辺の小さな町のがけの上の一軒家で暮らしていた。仕事で留守になりがちな父親の不在を寂しく思っていた宗介だったが、ある日、浜でさかなの子ポニョと出会う……#映画紹介#映画好きと繋がりたい pic.twitter.com/Znn1acU0jE— ひでじぃ (@paradox1042) July 26, 2025
「つまらない」「面白くない」という評価がある「崖の上のポニョ」。
では監督の宮崎駿氏は作中で何を伝えたかったのでしょう?
考察します。
母性や親子の絆の大切さ
「崖の上のポニョ」には、母親リサの包容力や家族との絆が随所に描かれています。
リサは宗介やポニョを優しく受け入れ、非常時にも落ち着いて家族を守る姿を見せます。
また、ポニョが人間になりたいと願う根底には「大好きな相手と一緒にいたい」「守りたい」という純粋な母性的な感情が感じられます。
こうした描写から、宮崎監督は親子や家族の無償の愛をテーマのひとつとして訴えかけていると言えるでしょう。
「生きること」への肯定
本作は「いのち」が中心テーマになっています。
ポニョが魚から人間への変身を希望し、宗介と心を通わせて冒険する過程には、生き物が本能的に成長しようとする意志や喜びがあふれています。
また、海の中でたくさんの命が描かれ、自然環境や生命循環についてもさりげなく示唆されています。
人として、子どもとして生きることの希望や素晴らしさを強調しており、「生きているだけで良い」「あるがままで大丈夫」というメッセージが込められているようです。
自然との共生・環境へのまなざし
「崖の上のポニョ」の大きな舞台は「海」であり、人間と自然との関係が物語の中核です。
ポニョが海の魔法の力で大洪水を起こしてしまったり、人間と自然界のバランスが崩れる描写は、現代社会の環境破壊や自然災害を彷彿とさせるものです。
その中で、宗介やリサ、ポニョが自然の理を受け入れ、再び調和を目指して行動する姿から、宮崎監督は人類と自然とが互いに補い合って生きるべきだというメッセージを発信していると考えられます。
子どもらしさの肯定と自由な想像力
本作品を通して特に強調されているのは、「子どもは世界をどう受け入れるのか」という視点です。
説明不足や論理の飛躍と思われる場面も、子どもたちの「わくわく」や「信じる力」「好奇心」を映し出していると解釈できます。
難しい理屈は抜きにして、五感や直感で物語を受け止める楽しさが最優先されているのです。
現実世界では困難に感じるような局面も、大人の理屈より「こうだったらいいのに」と思う子どもの自由な発想を肯定して、それを物語の軸としています。
まとめ
「崖の上のポニョ」(2008)
▶https://t.co/JzSuOTYnpv
宮崎駿監督が手がけた長編アニメーション。アンデルセン童話「人魚姫」をモチーフに、人間になりたいと願うさかなの女の子・ポニョと、心優しい5歳の少年・宗介の交流と冒険を描いたファンタジー。#AllTimeBest1200— 映画.com (@eigacom) July 29, 2025
「崖の上のポニョ」は、一見しただけでは「つまらない」「駄作」と受け取られることもありますが、その理由の多くは大人の視点や従来のジブリ作品との比較、説明不足ゆえの戸惑いにあります。
しかし作品全体を通じて描かれているのは、「生きることの肯定」や「家族や自然との調和」、そして「子どもが持つ純粋な想像力と希望」です。
宮崎駿監督が描きたかったのは、論理や整合性よりも「子どもの目線で、ありのまま世界を楽しむこと」だったのかもしれません。
大人が忘れがちな「無条件の愛」や「感性の自由」を思い出させてくれる――それが「崖の上のポニョ」の本当の魅力であり、伝えたいメッセージなのではないでしょうか。
最後までご覧いただきありがとうございました!